
市原市で制服リユース活動を続ける大岩さん。不登校を経験した我が子への想いが、地域を巻き込む温かい支援の輪を広げています。「高価な制服が無駄になるかも…」そんな悩みに寄り添い、制服に込められた「誰かの気持ち」を届けたい。大岩さんの原動力は、同じ苦しみを味わう家族に「あなたは一人じゃない」と伝えたいという強い想い。一人の母親の優しさが、市原市の未来を照らします。 取材日 2025年3月7日/文 Akari Tada
つなぐTsunagu ♡子育て世代の市民活動 代表
年齢 46歳
移住時期 2008年
移住エリア 南総地区
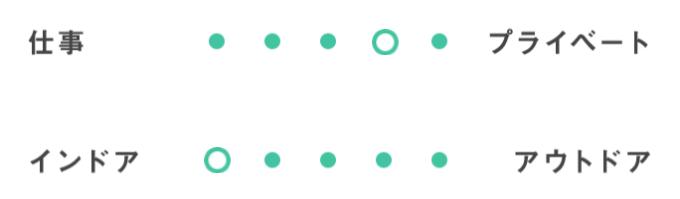
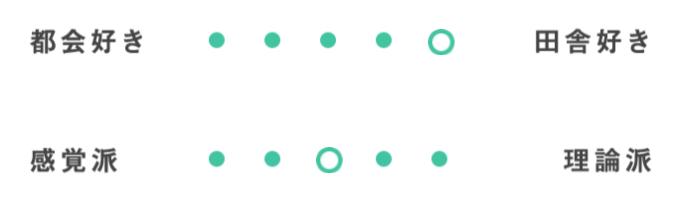
「子どもが学校に行かなくなった時、本当に落ちるところまで落ちました」と穏やかな表情で語るのは、市原市南総地区で制服リユース活動を行う大岩さん。2022年から始めたこの活動は、制服やジャージ、学用品を無償で必要な家庭に届けるもの。南総地区社会福祉協議会と連携し、地域に根差した支援の輪を広げています。しかし、その活動の裏には、単なる物資提供を超えた深い想いが込められていました。
活動のきっかけは、自身の子どもの不登校体験でした。「不登校家庭の教育費はほぼ実費。学校へ行くか行かないかわからないのに、制服や学用品購入で更に費用はかさみます。先輩からジャージを譲り受けたりしたことがとてもありがたかった」と大岩さんは振り返ります。
そんな経験から、同じ悩みを抱える家庭の助けなれたらという思いが芽生えました。また、SDGsの理念が広がる時代背景も追い風となりました。「学校でもSDGsの取り組みが始まった頃で、活動内容がちょうどマッチしたんです」と大岩さんは説明します。
しかし、それ以上に大岩さんの心を動かしたのは、「不登校当事者と繋がりたい」という強い願いでした。「友達もいなく、不登校の話をできる人も周りにいなくて孤独だった」という自身の経験から、同じ境遇にある家族同士で寄り添いたいと考えたのです。
制服リユースの活動が本格化したのは、大岩さんがPTA活動に疑問を感じたことがきっかけでした。「子どもが学校に行っていなくても、PTAの役員は回ってくる。でも学校の中のことがわからない」と当時の葛藤を語ります。
自分の子どもが学校外で体験していることを大切にしたい一方で、「あまりにも不登校に関する情報が少なすぎた」と大岩さんは気づきました。そこで、学校の先生方やPTA会長とコミュニケーションを取り、少しずつ知り合っていく中で「学校外で団体を作り、学校と連携した方がやりやすいのでは」という結論に至りました。
「不登校の歴史を調べたら、30年以上この状態が続いていることがわかったんです。自身の子育てが至らなかった部分はもちろんあります。けれど、不登校の課題はもっと本質的なところにある」と大岩さんは考えました。教育現場と当事者が協力し合える場が必要だという思いから、団体の立ち上げを決意したのです。
「家族の協力のもと立ち上げは1人で行いましたが、市役所に相談を持ちかけた時に担当してくれたのが、私が拠点とする南総地区出身の方だったんです」と大岩さんは語ります。市街地から離れた田舎ならではの不便さや閉塞感の中で子育てをする親の実情、活動を始めることの難しさに共感してくれる職員との出会いが、大岩さんの背中を強く押しました。
「こんなに親身に話を聞いてくれる人がいるんだと衝撃を受けました」と大岩さんは当時を振り返ります。子どもの不登校で苦しんでいた時期、「どこまで信じていいのか、力になってくれるのだろうか」と不安でいっぱいだった大岩さんにとって、理解ある職員との出会いは大きな転機となりました。「この出会いがなければ前を向けなかった。踏み切れなかった」と大岩さんは力強く語ります。
制服リユース活動の裏には、「不登校の当事者と繋がっていきたい」という大岩さんの強い思いがあります。「一番辛いのは不登校の初期の段階。そこでどんな人と出会い、どんな選択肢が持てるかでその後が大きく変わるんです」と大岩さんは説明します。
しかし、不登校に直面した家庭が自ら「助けてください」と声を上げるのは非常に難しいこと。「自分の子育てが悪かったのではないかと思い込んでしまったり、そもそも誰かを頼ることが必要だと気づかなかったりするんです」と大岩さんは語ります。
そこで、制服や学用品という学生生活に必要不可欠なものを通じて繋がりを作る方法を考えました。「行き渋りが始まった段階で、学校の先生に『こんな団体があるよ』とチラシを渡してもらい、不登校の親が相談し合える場があることを知ってもらう。そうして困っている人との繋がりを増やしていきたい」というのが活動の核心です。
これまでに約10人とつながり5人に制服やジャージを提供してきた大岩さん。「学用品の譲渡会でチラシを見て『実はうちの子が学校に行き渋っていて』と声をかけてもらえることもあります」と活動の手応えを感じています。
また、中学校の入学説明会でチラシ配布の協力を得られたことで、「もしも必要になった時には連絡をください」という周知ができ、実際に4件ほどの問い合わせがあったといいます。
南総地区社会福祉協議会とも協力し、なのはな館で試着もできます。
課題としては、女子制服は比較的充実しているものの、男子の学ランが不足していること。「丈や首元などなかなかフィットするサイズに出会うのが難しい上に、学ランは高校でも需要があるようで、出回る数も少ないんです」と大岩さんは説明します。
大岩さん自身が子どもの入学の際にかかった費用は約10万円。「昔は『節目には新しいものを』という考えだったけど、今は『綺麗なものは使っていこう』という世の中になっています。お下がりというのも誰かが気にかけてくれているから回っていくもの。その気持ちが嬉しいんです」と大岩さんは微笑みます。
南総地区は歴史も深く、古き良きものを大切にする村の文化が残っています。結婚を機に県外から移住してきた大岩さんは「きっと私は異質だと思います」と笑います。
制服を循環させるという活動は、地元商店街の仕事を奪ってしまう可能性もあり、最初は難しい面もありました。しかし、制服を取り扱うお店も少子高齢化の波を受け、時代の流れと共に事業を縮小するタイミングでした。南総地区社会福祉協議会と連携し丁寧に挨拶へ伺い、事業を進めることができました。「南総地区で歴史を築いてきた方々へ失礼のないよう、配慮しながら活動を進め、ご理解頂けるまでには時間が必要でした。」と大岩さんは振り返ります。
「支援をされている」と感じてしまうと相談や頼み事もしづらくなってしまうと考えた大岩さんは、「その人が求めているものは何か」を気軽に打ち明けられる、雑談ができるような場所を南総地区に作りたいと考えています。先日はなのはなフェスタに参加し、児童館などとも協力してその輪が広がっています。
「不登校当事者にならなければ、不登校が年々増加していることも知らなかったし、それが市原市の課題になっているということも気づかなかった」と大岩さんは正直に語ります。
様々な家庭環境の中で、少しでも助けになれる部分があればと始めた活動は、今では市原市内の各地域へと広がりつつあります。「私の願いは、こういう活動が地区ごと、学区ごとにできるようになること」と大岩さんは目を輝かせます。
実際に、南総地区の社会福祉協議会に学ランが足りないと相談したところ、他地区の社会福祉協議会から「校章の刺繍を外せば使えるよ」と提供してもらえたこともあったといいます。
「地区ごとに制服や学用品事情を把握して活動してくれる人や団体が増えれば、在庫の行き来は社会福祉協議会に任せて、市原市全体が子どもたちに平等に学習の機会を提供できるようになるはず」と大岩さんは未来を見据えます。
県外から市原市に移住してきた大岩さんが、自身の不登校経験から生み出した活動は、今や地域を繋ぐ大切な架け橋となっています。制服リユースという形を通じて、市原市の子育て世代を温かく包み込む大岩さんの活動は、この地域に新たな絆を生み出し続けています。
「誰かが気にかけてくれているから回っていくもの。その気持ちが嬉しい」という大岩さんの言葉には、人と人との繋がりを大切にする市原市の温かさが表れているのかもしれません。